【Live配信 or アーカイブ配信】CVD/ALDプロセスの反応解析、メカニズムとプロセス最適化
| イベント名 | CVD/ALDプロセスの反応解析、メカニズムとプロセス最適化 |
|---|---|
| 開催期間 |
2025年05月30日(金)
~ 2025年06月10日(火)
【Live配信】2025年5月30日(金) 10:30~16:30 【アーカイブ(録画)配信】 2025年6月10日まで受付(視聴期間:6月10日~6月20日まで) |
| 会場名 | ZOOMを利用したオンライン配信 ※会場での講義は行いません |
| 会場の住所 | オンライン |
| お申し込み期限日 | 2025年06月09日(月)15時 |
| お申し込み |
|
<セミナー No.505405>
CVD/ALDプロセスの
反応解析、メカニズムとプロセス最適化
★装置内の化学反応、流れと熱の解析から成膜機構を解説!
★意図する特性の薄膜を成膜するためのプロセス最適化の考え方を学ぶ
------------------------------------------------------------------------------------------------
■講師
反応装置工学ラボラトリ 代表 羽深 等 氏
■聴講料
1名につき55,000円(消費税込・資料付き)
1社2名以上同時申込の場合1名につき49,500円(税込)
大学、公的機関、医療機関の方には割引制度があります。詳しくはお問い合わせください。
■セミナーの受講について
・下記リンクから視聴環境を確認の上、お申し込みください。
→ https://zoom.us/test
・開催数日前または配信開始日までに視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。
セミナー開催日時またはアーカイブ配信開始日に、視聴サイトにログインしていただきご視聴ください。
・出席確認のため、視聴サイトへのログインの際にお名前、ご所属、メールアドレスをご入力ください。
ご入力いただいた情報は他の受講者には表示されません。
・開催前日または配信開始日までに、製本したセミナー資料をお申込み時にお知らせいただいた住所へお送りいたします。
お申込みが直前の場合には、開催日または配信開始日までに資料の到着が間に合わないことがあります。
・本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。
・本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。
複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。
・アーカイブ配信セミナーの視聴期間は延長しませんので、視聴期間内にご視聴ください。
プログラムあああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
【本講座で学べること】
1.CVD法とALD法の基本現象
2.熱流体と反応場の捉え方
3.気相化学種と膜組成、膜質から推定される化学反応
4.成膜結果の関数化表現と活用例
5.副生成物の挙動と影響
6.最適化の考え方
7.成膜装置全体で実際に生じている現象の全体像
8.装置部材、センサーなどが晒される状態
9.装置状態の検知と管理の要点
【講座概要】
化学気相堆積(CVD)法と原子層堆積(ALD)法は、様々な薄膜を形成する際に広く用いられている方法です。これは、流れ、熱、反応物質の輸送に気相・表面の化学反応が絡む現象であるため、難しく見えて来ます。そこで成膜装置で起きている化学反応と熱と流れの解析法、その場観察法、膜の分析法を紹介します。次に、それらを用いて成膜機構を解析し、設計し、検証した事例を紹介します。複雑に見えるプラズマ成膜の解析事例、排ガス管内堆積物から見える成膜現象、なども紹介します。これらは実務において、成膜装置全体で実際に生じている現象の全体像をとらえ、装置内の部材やセンサーなどが晒される状態を推定し、適切に検知して維持・管理に繋げることに繋がります。最後に、CVDプロセスを最適化する要点を議論します。装置、反応とプロセスを進歩させる契機になれば幸いです。
1.序論
1.1 MOSFETの構造と動作、半導体製造工程
1.2 CVD法とALD法の原理、成膜理由、装置、事例、条件と要因
1.3 微細化と成膜方法の使い分け
2.化学反応速度の基礎
2.1 化学反応の基礎と反応速度式の考え方
2.2 律速過程
3.表面反応・気相反応
3.1 表面反応・気相反応
3.2 反応の場所、物性と膜質の関係
4.その場観察方法
4.1 その場観察で得られる情報の例
4.2 ガス採取場所の選択と注意
4.3 主な方法:四重極質量分析法、圧電性結晶振動子法、赤外分光法
5.膜の分析方法
5.1. 膜厚・反応・膜質に関わる測定方法
5.2 X線光電子分光法、 赤外分光法・ラマン分光法、 二次イオン質量分析法、エネルギー分散型X線分光法
5.3 分析結果の解釈に困った時
6.反応の場を考慮した反応解析事例
6.1 流れを把握する必要性、流れの方向と膜厚の関係
6.2 CVD装置内のガス流れなど:観察例と数値計算例
6.3 ガス密度による流れの違い(観察例と計算例)
6.4 成膜最低温度決定(観察例)
6.5 装置の形とドーパント濃度分布(実測と解析)
6.6 基板回転の効果(膜厚平均化、流れの引寄せによる成膜高速化)
6.7 ALD装置内の流れと熱(数値解析例)
7.膜分析とガス分析の活用事例
7.1 排ガス分析と数値解析による成膜反応とドーピング反応のモデル構築
7.2 前駆体相互作用(クロロシラン、メチルシラン、三塩化ホウ素)の解釈、反応設計と検証の例
7.3 炭化ケイ素成膜機構の例
7.4 窒化ガリウム成膜機構の例
7.5 プラズマCVDによる多元系成膜の解析例(成膜条件から結果を予測し難い理由)
8.副生成物から推定される反応機構
8.1 排ガス管内堆積物
8.2 クロロシランによるSiとSiCの成膜時の堆積物
9.最適化の考え方
9.1 装置内全体の反応と堆積物
9.2 副生成物から推定される成膜反応状態
9.3 装置クリーニングと装置部材の耐腐食性
9.4 諸成膜要因の効果と活用(温度、濃度、流量、律速過程、回転)
9.5 解析・モデル化の進め方(要因の発見、法則と機構の決定)
10.まとめ
セミナーの詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
2名以上同時にお申込される場合、2人目以降の方の情報は【弊社への連絡事項がございましたら、こちらにお書きください】欄にご入力をお願いいたします。
- サイト内検索
- セミナー・書籍新着情報
-
- 【書籍】封止・バリア・シーリングに関する材料,成形製膜,応用の最新技術(No.2101BOD) (2025年04月30日)
- 【Live配信セミナー 6/16】新規事業テーマ,アイデア創出における生成AIの創造的活用 (2025年04月21日)
- 【Live配信セミナー 6/12】電子実験ノート活用への仕組み作りと定着のポイント (2025年04月21日)
- 【Live配信セミナー 6/9(アーカイブ配信付き)】時系列データによる将来予測,異常検知への応用 (2025年04月21日)
- 【Live配信セミナー 5/30(アーカイブ配信付き)】生成AI,AI開発におけるベンチャー企業との共同研究開発の進め方,留意点 (2025年04月21日)
- カテゴリー別
- 技術情報協会アーカイブ



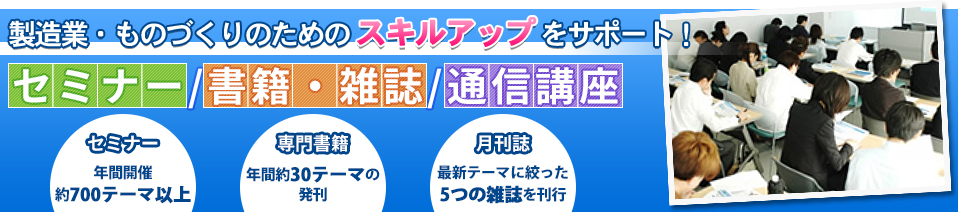

![足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内] 足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内]](https://www.atengineer.com/pr/gijutu/color/images/btn_wps.png)