| イベント名 | 放熱ギャップフィラーの特性、選定方法と効果的な使い方 |
|---|---|
| 開催期間 |
2025年06月17日(火)
10:30~16:15 |
| 会場名 | ZOOMを利用したLive配信 ※会場での講義は行いません |
| 会場の住所 | オンライン |
| お申し込み期限日 | 2025年06月16日(月)15時 |
| お申し込み |
|
<セミナー No.506403>
放熱ギャップフィラーの
特性、選定方法と効果的な使い方
★各種TIMの特徴や機能、最適な選び方、実際の製品での使われ方を学ぶ
------------------------------------------------------------------------------------------------
■講師
1.(株)ザズーデザイン 代表取締役 柴田 博一 氏
2.ヘンケルジャパン(株) オートモーティブコンポーネンツ事業部 シニアアプリケーションエンジニア 奥原 昂 氏
3.ペルノックス(株) 開発統括部 開発管理グループ グループリーダー 佐々木 雄一 氏
■聴講料
1名につき60,500円(消費税込・資料付き)
1社2名以上同時申込の場合1名につき55,000円(税込)
大学、公的機関、医療機関の方には割引制度があります。詳しくはお問い合わせください。
■Live配信セミナーの受講について
・下記リンクから視聴環境を確認の上、お申し込みください。
→ https://zoom.us/test
・開催日が近くなりましたら、視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
・Zoomクライアントは最新版にアップデートして使用してください。
Webブラウザから視聴する場合は、Google Chrome、Firefox、Microsoft Edgeをご利用ください。
・セミナー資料はお申込み時にお知らせいただいた住所へお送りいたします。お申込みが直前の場合には、開催日までに資料の到着が間に合わないことがあります。ご了承ください。
・当日は講師への質問することができます。可能な範囲で個別質問にも対応いたします。
・本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。
・本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。
・Zoomのグループにパスワードを設定しています。部外者の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。万が一部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。
プログラムあああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
<10:30~12:00>
1.ギャップフィラーを含むTIMの特性と選定方法
(株)ザズーデザイン 柴田 博一 氏
【本講座で学べること】
・TIMを価格や単純な熱伝導率だけでなく、特性から最適な製品を選定ことが出来るようになる
・現在市販されている幅広いTIMの違いを把握する
・実際の使用例からTIMの使い方を学ぶ
【講座概要】
電気・電子機器の消費電力上昇に伴い、幅広い製品にTIM (Thermal Interface Material) が使われるようになってきた。各種用途に応じた多種多様なTIMが市販されているが、その特性を十分理解し、最適な製品を選定するためには、熱設計に関する基礎的な知識を必要とする。一方でTIMはその構成要素であるバインダーとフィラーの材料特性をきちんと把握することで、その性能をより深く理解することができるようになる。本セミナーはTIMの熱的特性と機械的特性の二つの面からTIMの特性を把握し、さらに実際の製品での使われ方を参照することで使用方法のコツを短時間に習得することを目的とする。
1.TIMをより理解するための電熱の基礎
1.1 放熱の基本となる熱移動の3要素
1.2 熱伝導とは
1.3 熱抵抗とは
1.4 熱抵抗の直列と並列
2.TIMの特性と選定方法
2.1 TIMの構成要素
2.2 TIMの熱的特性
2.3 TIMの機械的特性
2.4 最終的に何に注目してTIMを選ぶのか
2.5 TIMの高性能化
3.実際のTIMの使用例
3.1 スマートフォン
3.2 グラフィックボード
3.3 車載用バッテリー
-------------------------------------------------------------------------------
<13:00~14:30>
2.放熱ギャップフィラーおよび熱伝導性接着剤の特性と自動車熱マネジメントへの応用
ヘンケルジャパン(株) 奥原 昂 氏
【本講座で学べること】
・熱伝導性材料の機能と役割
・熱伝導性材料の種類(シート、1液、2液)とそれぞれの特徴
・二液性液状ギャップフィラーの特徴と利点
・熱伝導性接着剤の特徴と利点
・次世代エネルギー車用部品の熱マネジメント材料に求められる特性
【講座概要】
自動車産業は今、世界的に100年に一度の変革期を迎えていると言われており、この自動車産業の変革をリードする技術として最も注目を浴びているのが「次世代エネルギー車」である。次世代エネルギー車、いわゆるEVに使用される材料の1つである熱マネジメント材料は、駆動用バッテリーやパワーコンバージョン部品に無くてはならない機能性材料で、ここ数年かつてないほどの活況を呈している。
そこで本講演では代表的な熱マネジメント材料である放熱ギャップフィラーおよび熱伝導性接着剤の特性と、次世代エネルギー車における適用事例を紹介する。
1.次世代エネルギー車用部品の熱対策
1.1 自動車産業におけるトレンド
1.2 次世代エネルギー車用部品の熱マネジメント課題
2.放熱ギャップフィラーの紹介
2.1 TIM (Thermal Interface Material) の機能と役割
2.2 TIMの種類と各機能
2.3 放熱ギャップフィラーの性能
2.3.1 放熱ギャップフィラーの特徴および利点
2.3.2 シート材料との比較
2.3.3 一液材料との比較
3.放熱ギャップフィラーの採用実績
3.1 EVバッテリーでの採用実績
3.2 パワーエレクトロニクス部品での採用実績
4.熱伝導性接着剤の採用実績
4.1 パワーエレクトロニクス部品での採用実績
4.2 CTP (Cell to Pack) への応用
5.まとめ
-------------------------------------------------------------------------------
<14:45~16:15>
3.ウレタン系放熱ギャップフィラーの開発とその特性
ペルノックス(株) 佐々木 雄一 氏
【本講座で学べること】
・ウレタン配合技術の基礎
・材料評価
【講座概要】
近年、電子機器の高性能化、小型化による高密度実装化が進み、多くの部品やユニットにおいて熱対策が重要な課題となっている。熱対策には、熱伝導、対流、熱放射の手段がある。TIM(Thermal Interface Material)には、電子部品から発生する熱の排熱のために、高熱伝導化が求められている。熱伝導材料は、信頼性や界面熱抵抗の観点から、シリコーン系が主流となっている。しかし、シリコーン系にもいくつかの課題があるため、ウレタン系TIMの選択肢を示すとともに、配合技術の基礎について解説する。
1.放熱材料の種類と市場及び用途
1.1 伝熱メカニズムと種類
1.2 市場と用途
2.ウレタン系TIMの材料構成と構造
2.1 ポリオール
2.2 鎖延長剤
2.3 イソシアネート
2.4 触媒
2.5 添加剤
2.6 熱伝導フィラー
2.7 構造
3.ウレタン系TIMの特長と評価
3.1 特長
3.2 熱抵抗と熱伝導率
3.3 振動吸収性
4.ウレタン系TIMの課題
4.1 耐久性/信頼性
4.2 量産設備への適合性
5.ウレタン系TIMの性能
5.1 プロトタイプ品の性質
5.2 耐久性
5.3 ブリードアウト
6.更なる高熱伝導化
6.1 フィラーの最密充填
6.2 特性
7.まとめ
セミナーの詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
2名以上同時にお申込される場合、2人目以降の方の情報は【弊社への連絡事項がございましたら、こちらにお書きください】欄にご入力をお願いいたします。
- サイト内検索
- セミナー・書籍新着情報
-
- 【Live配信セミナー 8/19】樹脂・プラスチックにおける「低塩素化」,「ハロゲンフリー」 に関する材料設計,各種分析・解析,その応用 (2025年06月15日)
- 【Live配信 or アーカイブ配信】~Microsoft Excelを用いた~攪拌プロセスの予測・計算の 進め方,その応用 (2025年06月14日)
- 【Live配信 or アーカイブ配信】有機EL(OLED),μOLED,μLED,液晶,量子ドットなどの次世代ディスプレイ技術の現状と展望 (2025年06月14日)
- 【Live配信セミナー 8/7】ふるい分け操作の最適化とトラブル対策および応用技術 (2025年06月14日)
- 【Live配信セミナー 8/6】光硬化に用いられる『光重合開始剤』とその『助剤』の種類,選び方,使い方,暗所・深部・厚膜硬化,速硬化への対応 (2025年06月14日)
- カテゴリー別
- 技術情報協会アーカイブ



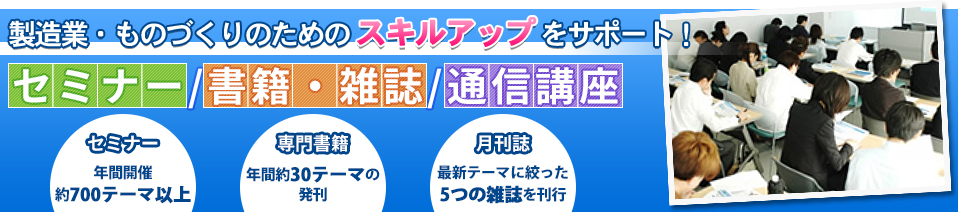

![足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内] 足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内]](https://www.atengineer.com/pr/gijutu/color/images/btn_wps.png)