【Live配信セミナー 8/25】知財戦略、知財活動の評価と経営層への報告、アピールの仕方
| イベント名 | 知財戦略、知財活動の評価と経営層への報告、アピールの仕方 |
|---|---|
| 開催期間 |
2025年08月25日(月)
10:00~17:15 |
| 会場名 | Zoomを利用したLive配信 ※会場での講義は行いません |
| 会場の住所 | 東京都 |
| お申し込み期限日 | 2025年08月24日(日)15時 |
| お申し込み |
|
<セミナー No.508505>
【Live配信】
知財戦略、知財活動の評価と
経営層への報告、アピールの仕方
★知財活動をどのように定量的・定性的に評価するのか!
★経営層が求める貢献度とは何か!どのように知財部門の存在感を高めるか!
----------------------------------------------------------------------------------
■講師
【第1部】ナガセケムテックス(株) 経営管理本部 業務推進部 知財担当部長 冨田 光治氏
【第2部】 (一社)京都発明協会、専務理事 原 伸郎氏
【第3部】一級知的財産管理技能士(特許専門業務) 宮下 洋明氏
【第4部】ローム(株) 知的財産部 アソシエイト・フェロー 山本 勲氏
■聴講料
1名につき66,000円(消費税込み、資料付)
1社2名以上同時申込の場合1名につき60,500円(税込)
大学、公的機関、医療機関の方には割引制度があります。
詳しくはお問い合わせください。
プログラム
【10:00~11:30】
【第1部】経営に資するグローバル知財活動と経営層への説明、アピールのポイント
ナガセケムテックス(株) 経営管理本部 業務推進部 知財担当部長 冨田 光治氏
【講師略歴】
大阪府立大学大学院 農学研究科 修士課程修了後、大手化学メーカー入社。食品研究部、特許部を経て、2001年 ナガセケムテックス株式会社入社。同社の知財・法務部署の立ち上げに参画し、平成18 年弁理士登録、知的財産室室長として国内外特許実務全般、知財戦略、知的財産等に関わる技術契約の審査等の様々な知財業務に従事。2025年4月より現職。
【講演趣旨】
企業では、国際競争が激しくなる中、技術開発の成果である知的財産(知財)をどのように保護、活用していくかは重要な問題です。経済のグローバル化により、企業は諸外国へ積極的に進出することが必要となっています。 昨今では、既に国内で事業化された製品を海外展開するだけでなく、開発段階から海外での展開を見据えた製品開発を行うことも求められてきており、経営に資するグローバルな知財活動が求められています。 しかし、多くの企業の知財担当者は社内の経営層に対し知財の重要性の理解を得ることに苦慮しているのではないでしょうか。 そこで、本セミナーでは、経営に資するグローバル知財活動(主に特許を中心とした知財活動)と経営層への説明、アピールのポイントについて解説します。
【講演項目】
1.経営に資するグローバル知財活動(主に特許活動を中心に)
1.1 なぜグローバル知財活動が重要なのか
1.2 外国特許を取得する手段
1.3 各国の特許制度の違い
1.4 グローバル知財戦略の進め方
1.5 海外展開における知財リスクとその管理
1.6 海外関係会社との連携
1.7 グローバルな技術トレンドへの対応
2.経営層への説明、アピールのポイント
1.1 経営層との連携の必要性
1.2 経営層が重視する視点
1.3 経営層への働き掛け
1.4 経営層からいかに理解を得るか
【質疑応答】
---------------------------------------------------------------
【12:15~13:45】
【第2部】知財活動の見える化でコストと価値を経営資源に
(一社)京都発明協会、専務理事 原 伸郎氏
【講師略歴】
1985年4月 日本写真印刷株式会社(現NISSHA株式会社)入社
2010年4月 同社 知的財産部 部長
2022年4月 一般社団法人京都発明協会 INPIT京都府知財総合支援窓口 事業責任者
2024年4月 同法人 事務局次長
2024年6月 同法人 専務理事(現職)
【講演趣旨】
知財活動は特許出願や権利維持にとどまらず、社内教育、他社特許の監視、事業戦略との連携など多岐にわたります。しかし、その価値を正しく評価し経営層に伝えるのは容易ではありません。本講演では、知財活動の全体像を整理し、具体的な評価方法と落とし穴、戦略との結びつけ方、棚卸しと最適化の進め方を解説します。明日から実践できる「知財の見える化」で、知財部門を経営資源として活かすポイントを説明します。
【講演項目】
1.知財活動の全体像を理解する
1.1 知財活動の多様性
1.2 大企業と中小企業の知財の違い
1.3 既存事業における知財の役割
1.4 新規事業における知財の役割
1.5 知財活動が見える化されにくい理由
2.知財活動の評価方法を整理する
2.1 定量評価の考え方
2.2 KPI(重要業績評価指標)の活用
2.3 定性的評価の方法
3.知財戦略と評価をつなげる
3.1 知財戦略の基本構造
3.2 戦略に基づく評価指標の設計
3.3 部門連携の必要性と落とし穴
4.知財棚卸と保有資産の最適化
4.1 棚卸が必要な理由
4.2 棚卸の進め方
4.3 サンクコストの排除
4.4 放棄判断の基準と社内手続き
4.5 棚卸結果を経営層へ報告するコツ
4.6 棚卸を定期化する方法
5.経営層への伝え方と仕組み化
5.1 数字+ストーリーで伝えるポイント
5.2 経営層が求める「貢献度」とは
5.3 数字と役割をセットで示す報告術
5.4 報告を一度で終わらせない仕組み
5.5 オーソライズを取る文化づくり
【質疑応答】
---------------------------------------------------------------
【14:00~15:30】
【第3部】経営層への知的財産活動の伝え方 ~知的財産部門を一言で表現できますか?~
一級知的財産管理技能士(特許専門業務) 宮下 洋明氏
【講師略歴】
知的財産一筋24年。特許事務所、並びに、電器メーカー、食品メーカー及び化粧品メーカーの知的財産部門を経て、知的財産実務全般及び職制管理職を経験。前職及び現職では、知財活動方針・計画の立案・実行、人材育成、CGC対応組織の職制管理職に従事。トマト含有飲料事件(平成28年(行ケ)第10147号)を知財責任者及び代理人として遂行。JIPA、弁理士会等での研修講師活動、パテント誌への投稿多数。
【講演趣旨】
知的財産部門を一言で表現できますか。どのように経営層をして知財活動を理解してもらうか。それが皆さんの悩みであるとお察しします。知財紛争が盛んな業界であれば、知財活動の必要性を殊更論じなくとも、その必要性は理解してもらえるでしょう。他方、知財的には平和に見える業界では、上述のような悩みが生じてくるかもしれません。そこで、どのように知財活動の意義を伝えていくのか、3つの業界で知財部門を渡り歩いた筆者の経験を踏まえて、筆者の工夫をお伝えします。
【講演項目】
1.知的財産部門を一言で表現できますか?
2.どのように知的財産部門の存在感(プレゼンス、レリバンス)を高めるか
3.どの方向に知的財産部門は変化すべきなのか
4.知財部門よ、稼いで来い!
5.知的財産部門よ、成長の画を描け
6.何を期待されているのか、何ができるのか
7.何者かを意識していないと(自分が無いと)、巷の声に振り回される
8.当然できていることができているからこそ、仕事の幅が広がっていく
・当然できているよね
・できるんじゃない?
・へぇ、できるんだぁ
・何で、知財がやってるの(意味分かってる)?
9.当然できていることができていないのに、仕事の幅を広げていませんか
10.「当然できているよね。」に応えられていますか
11.権利取得は、経営者の期待通りにできていますか
12.権利活用は、経営者の期待通りにできていますか
13.侵害予防・対処は、経営者の期待通りにできていますか
14.契約締結は、経営者の期待通りにできていますか
15.調査分析は、経営者の期待通りにできていますか
16.そんなに存在意義、存在意義というのならば、戦いなさい
17.「当然できているよね。」に応えた後は
18.何か新しいことをしなければならないのでしょうか
19.言語化のやり方を変える
20.「できるんじゃない?」に応えながら、何をするか
21. 知的財産部門を一言で表現できましたか?
【質疑応答】
---------------------------------------------------------------
【15:45~17:15】
【第4部】IPLの実施体制と評価、経営層への報告ポイント
ローム(株) 知的財産部 アソシエイト・フェロー 山本 勲氏
【講師略歴】
1990年 日本大学文理学部応用物理学科卒業
1993年 ローム株式会社入社、アナログ、システムLSIの企画、開発、採用多数
2011年 電源系LSI商品開発部門長、プロダクトマネジメント部兼務
2015年 海外LSI設計会社経営統合プロジェクトリーダー兼務
2016年 アプリケーションエンジニア部門長
2019年 知的財産部
2023年 AIPE認定知的財産アナリスト(特許)取得 現在に至る
【講演趣旨】
近年の経営環境は急速な変化が続き、従来の延長線上に成長戦略を描くことはたいへん難しくなった。武力衝突、生成AIの開発競争、追加関税によるサプライチェーンの分断など、変化のスピードはますます加速している。その一方で経営の武器となるべき競争力を確保するには、長期視点に基づく技術の準備が欠かせない。従って知的財産情報と市場情報という異なる時間軸を包含した多角的分析であるIPランドスケープ(IPL)のニーズは高まる一方であろう。しかし実際の経営や事業に貢献したIPLはそう多くないというのが当社の実感である。本講座では事業に求められるIPL実現に向けた当社の模索を述べる。道半ばの取り組みが、みなさまのご参考になれば幸いである。
【講演項目】
1 半導体業界の特徴と当社を取り巻く環境
1.1 半導体業界の特徴
1.2 半導体技術と企業の推移
1.3 ロームの沿革
1.4 当社を取り巻く環境
2 当社におけるIPL
2.1 IPL推進のきっかけ
2.2 現在の実施体制
3 事業部に向けたIPL
3.1 浸透への取り組み
3.2 評価指標の導入
4 経営層に向けたIPL
4.1 知財戦略会議
4.2 経営層への報告ポイント
5 IPL事例
6 評価と分析結果
7 まとめ、今後の課題
【質疑応答】
セミナーの詳細についてお気軽にお問い合わせください。
2名以上同時にお申込される場合、2人目以降の方の情報は、
【弊社への連絡事項がございましたら、こちらにお書きください】欄に
ご入力をお願いいたします
◆Live配信セミナーについてのお願い◆
■お申込み前にご確認ください
・パソコンもしくはタブレット・スマートフォンとネットワーク環境をご準備下さい。
快適に視聴するには30Mbbs以上の回線が必要です。
・Zoomを使用されたことがない方は、ミーティング用Zoomクライアントをダウンロードして下さい。
ダウンロードできない方はWebブラウザ(Google Chrome、Firefox、Microsoft Edge)でも受講可能です。
Zoomの視聴にあたり、クライアントおよびWebブラウザは最新版にアップデートして使用してください。
・質問の際など、クリアな音声で会話ができるよう、ヘッドセット(イヤホンマイク)の使用をお勧めいたします。
・Zoomの使用方法につきましては、事前にWeb等でご確認ください。
下記公式サイトから視聴環境をご確認いただけます。
→視聴環境 https://zoom.us/test
■Live配信セミナーの受講について
・開講日の4~5日前に視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。
セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
・出席確認のため、視聴サイトへのログインの際にお名前、ご所属、メールアドレスをご入力ください。
ご入力いただいた情報は他の受講者には表示されません。
・開催前日着までに、製本したセミナー資料をお申込み時にお知らせいただいた住所へお送りいたします。
お申込みが直前の場合には、開催日までに資料の到着が間に合わないことがあります。
・当日は講師への質問をすることができます。
・本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。
・本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。
複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。
- サイト内検索
- セミナー・書籍新着情報
-
- 【Live配信セミナー 10/20】IPランドスケープの進め方と経営層,事業部への提案方法 (2025年08月15日)
- 【Live配信セミナー 10/15】生成AI×知財業務 実践講座 (2025年08月15日)
- 【Live配信セミナー 10/8】DXを活用した実験自動化と推進のポイント (2025年08月15日)
- 【Live配信セミナー 10/7】新規R&Dテーマを社内で通すための数字の示し方,経営層説明・説得の仕方 (2025年08月15日)
- 【Live配信 or アーカイブ配信セミナー】生成AIの著作権侵害問題とトラブル対策 (2025年08月15日)
- カテゴリー別
- 技術情報協会アーカイブ



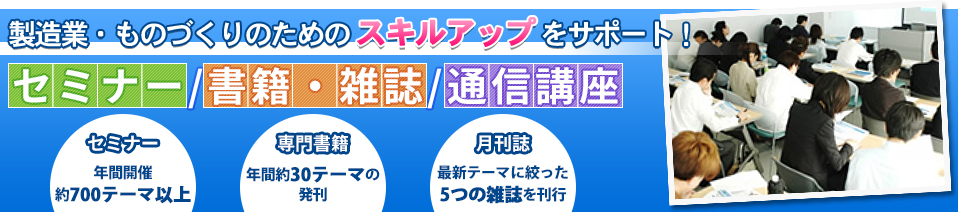

![足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内] 足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内]](https://www.atengineer.com/pr/gijutu/color/images/btn_wps.png)