| イベント名 | 高分子材料における微生物劣化のメカニズムと対策技術 |
|---|---|
| 開催期間 |
2025年09月30日(火)
2025年9月30日(火) 10:30~16:30 |
| 会場名 | [東京・五反田] 技術情報協会 8F セミナールーム |
| 会場の住所 | 東京都品川区西五反田2-29-5 日幸五反田ビル8F |
| 地図 | https://www.gijutu.co.jp/mailmap/company_map.htm |
| お申し込み期限日 | 2025年09月29日(月)15時 |
| お申し込み |
|
<セミナー No 509209>
高分子材料における
微生物劣化のメカニズムと対策技術
~インフラはすぐそばに/ 埼玉の道路陥没事故は対岸の火事ではない/地球環境悪化による高分子材料の微生物劣化とトラブルの解と予防対策~
★微生物やバイオフィルムから分泌される「酵素」が,なぜポリマー鎖を切断するのか?
★微生物の栄養になってしまう添加剤成分,空気の流れ,温湿度とは?
★軽視される「微生物耐性」,コーティング,薬品,防腐剤の選び方 使い方
■ 講 師
●講師:長岡技術科学大学 特化学物質評価研究機構 専務理事】
【受賞歴】
1995年, 2009年, 2018年 日本ゴム協会 優秀論文賞
2006年 マテリアルライフ学会 優秀論文賞
2009年 日本ゴム協会賞
2016年 プラスチック成形加工学会 優秀論文賞
2018年 オーエンスレーガン賞
■ 開催要領
日時:2025年9月30日(火) 10:30~16:30
会場:[東京・五反田] 日幸五反田ビル8F 技術情報協会セミナールーム
聴講料:1名につき55,000円(消費税込み,昼食・書籍付)
〔1社2名以上同時申込の場合のみ1名につ49,500円〕
〔大学,公的機関,医療機関の方には割引制度があります。詳しくはお問い合わせ下さい〕
プログラム
【講座の趣旨】.
埼玉・八潮市の道路陥没事故,博多駅近くの道路陥没事故,それらは下水管の老朽化だけではない。何れも充分な寿命を残しながら陥没していると言う事実は,日本の豊かな食生活を起因とした嫌気性硫酸還元菌が主要因である。
また,九州地区では上水道のジョイント部の微生物劣化,MDPEガスの微生物による物性低下現象が発現しつつある。これらは難分解性ポリマーと言われるPE等の合成樹脂が微生物の学習効果(馴養化)と近年の地球温暖化の相乗効果によって生じている。
本講座は,これらの現象を微生物の専門家で無くても理解出来るよう,微生物の実際の挙動から発現する現象,材料に与える影響,そして対策までを分かり易く,平易に解説する。本講を受講する事で「高分子における微生物劣化対策」のスペシャリストになれる事をお約束します。
【このような事が学べます】
(1)ゴム・プラスチックの事故事例(特に地球温暖化による微生物劣化)
(2)ゴム・プラスチックに追加した抗菌剤,防カビ剤の効用とトラブル
(3)ゴム・プラスチックの破損・破壊と対策
(4)ゴム・プラスチックの各種劣化因と対策
(5)地球環境悪化へのゴム・プラスチック材料の影響と対策
【セミナープログラム】
1.コンクリートの発生物破壊とエポキシコーティングの硫酸による劣化
1,1 なぜ,コンクリート設備が簡単に崩壊してしまうのか?
1.2 硫酸発生メカニズム
1.3 硫酸遼元と硫黄酸化細菌の相乗作用
1.4 なぜ,硫酸によるコンクリート破壊事故が激増しているか?
1.5 防食材としてのコンクリート表面のエポキシコーティングが耐久性への問題
1.6 エポキシ樹脂の耐薬品性
1.7 環境中の化学物質と適材適所の高分子材料の選択
1.8 ポリマーと硫酸,水などの侵入分子との関係
1.9 GERPの耐薬品性
1.10 コンクリートの強化と充分な曝気対策と有用な微生物の活用
2.学習する微生物 (制養化)によるゴム・プラスチックの事故
NR+SBR 製の導水管の微生物化
地球温暖化により,微生物活動の活性化に伴い,土壌中でのゴム・プラス
チックの耐久性が著しく低下している。その事例紹介と対策。
例えば,上水道管のつなぎ目部の ゴムの微生物劣化。 都市ガス配管 (MDPE)など
3.学習する微生物 (副養化) によるゴム・プラスチックの事故
3.1 PU製ビールサーバーパッキンのビール漏れ
3.2 PU製靴底の破損
3.3 LDPE製水道管スリーブの白化現象
3.4 エステル系 PU 靴底の崩壊事故
3.5 分子量測定
3.6 EPMA (Electronprobe Micro Analyzer) による
“P”元素の存在確認による微生物劣化の判定
3.7 エステル系 PU製ビールサーバー管の微生物劣化
3.8 土壌埋設された水道管用 LDPEスリーブの白化トラブル
(LDPEの微生物劣化分解)
3.9 アクチフェノールコットンブルー
(Lactphenoicotan bue) による微生物劣化の判定方法
3.10 馴養 (Adaptation) による微生物の学習効果
4.ゴム・プラスチックに添加した抗菌剤,防カビ剤の効用とトラブル
4.1 抗菌剤と防カビ剤は基本的には異なる
4.1.1 抗菌剤
4.1.2 防カビ剤
4.2 防カビ剤を原因とするトラブル(皮膚障害)
【質疑応答】
- サイト内検索
- セミナー・書籍新着情報
-
- 【Live配信セミナー 11/17】 核剤(結晶核剤),造核剤の種類と使い方,高分子の結晶化制御,各種応用,その評価法 (2025年09月08日)
- 【Live配信 or アーカイブ配信】「UV硬化」の硬化不良,トラブルの種類とその対策,硬化物性の測定評価 (2025年09月08日)
- 【Live配信 or アーカイブ配信】新しいリチウムイオン電池の電極構成,特性と材料&プロセス技術 ~双極子and全固体with乾式電極withoutバインダー~ (2025年09月08日)
- 【Live配信 or アーカイブ配信】乳化(エマルション),可溶化,ゲル化のメカニズム,乳化剤の種類と選定,安定化,その評価 (2025年09月08日)
- 【セミナー 11/6】微粒子の分散・凝縮メカニズム,安定化,評価 (2025年09月08日)
- カテゴリー別
- 技術情報協会アーカイブ



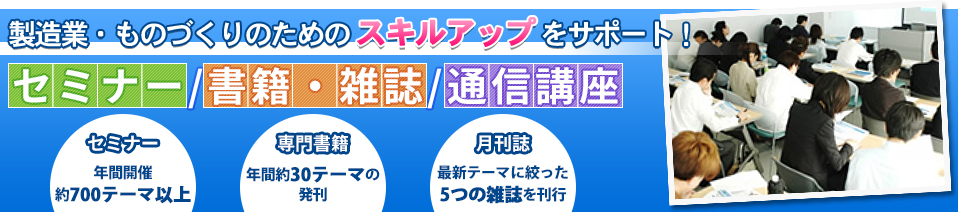

![足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内] 足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内]](https://www.atengineer.com/pr/gijutu/color/images/btn_wps.png)