| イベント名 | IPランドスケープの取り組み事例と実施体制の構築 |
|---|---|
| 開催期間 |
2025年12月05日(金)
~ 2025年12月08日(月)
12/5(金)10:30~16:15 12/8(月)11:00~16:15 |
| 会場名 | Zoomを利用したLive配信 ※会場での講義は行いません |
| 会場の住所 | 東京都 |
| お申し込み期限日 | 2025年12月04日(木)15時 |
| お申し込み |
|
<セミナー No.512502>
【Live配信】
<書籍発刊記念セミナー>
IPランドスケープの取り組み事例と
実施体制の構築
★IPL導入、社内普及の仕掛けと自社に合った実施体制、運用ポイント!!
----------------------------------------------------------------------------------
■講師
【第1部】第一工業製薬(株) 京都中央研究所 所長 正司 武嗣氏
【第2部】(株)IHI 技術開発本部 知的財産部 戦略グループ
グループ長 堀江 元氏
【第3部】日揮コーポレートソリューションズ(株) 知的財産部
エキスパート 笹岡 友陽氏
【第4部】味の素(株) 知的財産部 企画戦略グループ
シニアマネージャー 田澤 陽子氏
味の素(株) 知的財産部 企画戦略グループ
マネージャー 大西 愛氏
【第5部】(株)フジクラ 基盤技術センター 知的財産渉外部
主席研究員 東村 恵理氏
【第6部】ブラザー工業(株) 知的財産部
グループ・マネジャー 伊藤 隆氏
■聴講料
1名につき66,000円(消費税込み、資料付)
1社2名以上同時申込の場合1名につき60,500円(税込)
大学、公的機関、医療機関の方には割引制度があります。
詳しくはお問合せください。
プログラム
【12月5日(金) 10:30~12:00>】
【第1部】第一工業製薬における知財インテリジェンス活動の取り組み
第一工業製薬(株) 京都中央研究所 所長 正司 武嗣氏
【講師略歴】
新卒で第一工業製薬株式会社に入社、約10年の研究開発を経て知的財産部門に異動。出願権利化や調査等の業務を担当。 2013年弁理士登録。2021年から知的財産部長。知財問題について社内外との調整・交渉や、IPランドスケープも活用した社内外との対話、等を担う。 2025年から知的財産部門や基礎研究部門を統括する京都中央研究所の研究所長。研究や事業側の立場から知財部門の在り方について検討を進めている。
【講演趣旨】
企業において知財担当部門は、特許の出願・権利化等のプロセスを通じて、自社の技術情報を全体的かつ俯瞰的に把握している。「情報」を継続的に取り扱っている知財担当部門が知財インテリジェンス活動を担うことは、自然な流れである。 知財インテリジェンス活動の実践ツールといえるIPランドスケープが注目されていているが、実際自社の事業において活用し、経営戦略等に落とし込み、さらに売り上げや利益面での金銭的な成果を得ようとすると、ハードルが高い、という声も聞こえる。 そこで、講師の実務を通じて見えてきた課題や、研究や事業側の立場からの知財部門への期待を含めて、導入から実践と活用までの流れを紹介することで、自社にとって最適なアプローチを探る材料を述べていきたい。
【講演項目】
1.なぜ今、知財インテリジェンス活動とIPランドスケープなのか
1.1 知財インテリジェンス活動
1.2 IPランドスケープ
1.3 第一工業製薬について
1.4 企業の知財的課題との関係
1.5 知財インテリジェンス活動とIPLの始め方
2.知財インテリジェンス活動とIPLの実践
2.1 目指すべき方向性とIPLの活用法
2.2 知財部門内でのIPLの活用
2.3 IPLを活用した事業部門との対話
2.4 IPLを活用した経営層との対話
2.5 IPLを活用した社外との対話
3.普及・実践の課題と対応
3.1 よくある課題
3.2 課題への対応
4.まとめ
【質疑応答】
---------------------------------------------------------------
【12月5日(金) 13:00~14:30】
【第2部】IHIにおけるIPランドスケープ普及に向けたこれまでの歩み
(株)IHI 技術開発本部 知的財産部 戦略グループ グループ長 堀江 元氏
【講師略歴】
大手半導体メーカーの知的財産部門を経て株式会社IHIに入社。技術開発本部知的財産部にて実務遂行や各種業務改革の企画推進等を行った後、IPランドスケープの取り組みを推進。その後、経営企画部にて経営戦略・経営管理に携わり、2025年4月より知的財産部戦略グループのグループ長。現在、経営企画の視点や経験を活かしながらIPランドスケープの社内普及と更なる高度化に取り組んでいる。
【講演趣旨】
IHIは、知的財産情報の分析を駆使して事業戦略や技術戦略に寄与するべくIPランドスケープに取り組んできた。本講演では、IHIにおけるIPランドスケープ導入の経緯、具体的な普及活動、そして現在の状況と今後の課題を説明する。特に導入初期の苦労や、一定の認知と普及に至る中で重要だったと考えられる取り組みを解説し、日本企業がIPランドスケープを導入・定着させていくための一助となる示唆を提示したい。また、今後のアナリストの育成やIPランドスケープの位置づけという課題についても触れ、議論してみたい。
【講演項目】
1.株式会社IHIについて
2. IPランドスケープ普及を進める知的財産の組織体制について
2.1 知的財産部
2.2 知財マネジメント体制
3.IHIにおけるIPランドスケープの導入
3.1 導入当時の状況とIPランドスケープの導入のきっかけ
3.2 導入当初の体制
3.3 導入当初の状況と課題
4.IHIにおけるIPランドスケープ普及への挑戦
4.1 技術戦略を軸としたアプローチ
4.2 アナリストの中途採用等を活用した体制強化
4.3 知的財産部外への人材の異動によるIPランドスケープの普及
4.4 人材育成プログラムへのIPランドスケープの組み込み
4.5 社外有識者の活用によるアプローチ
4.6 各事業部門・技術開発部門における知財活動方針へのIPランドスケープの入れ込み
4.7 従来の知的財産業務の仕組みへのIPランドスケープの入れ込み
5.現在の状況と今後の課題
5.1 現在の状況
5.2 今後の課題
6.まとめ - 日本企業におけるIPランドスケープ普及のために
【質疑応答】
---------------------------------------------------------------
【12月5日(金) 14:45~16:15>】
【第3部】日揮グループにおける知財インテリジェンス活動と知財戦略の実行
日揮コーポレートソリューションズ(株) 知的財産部 エキスパート 笹岡 友陽氏
【講師略歴】
2001年にトヨタ自動車株式会社に入社。燃料電池、CFRP、全固体電池の開発、企画に従事。2014年に経済産業省特許庁に入庁。審査官として燃料電池・電動車両システム等の特許審査を担当。デザイン経営プロジェクト、I-OPENプロジェクトに参画。2024年に日揮ホールディングス株式会社に入社。日揮コーポレートソリューションズ株式会社知的財産部に勤務。弁理士、AIPE認定知的財産アナリスト(特許)。
【講演趣旨】
日揮グループでは、知的財産を価値創造の源泉と位置づけ、事業戦略・開発戦略と連動した知財戦略を推進しています。IPランドスケープを軸に、事業部門・開発部門と連携した知財インテリジェンス活動を通じて、日揮グループ内外の知の創造と融合の活性化を図っています。風通しのよい企業文化のもと、「対話」と「スピード」を重視し、インハウスの知的財産部門ならではの質実剛健なIPランドスケープを目指しています。本講演では、知財インテリジェンス機能の構築と運用、社内浸透の工夫、活動の評価・改善、そしてコア事業・新規事業・製造子会社との連携によるシナジー創出など、日揮グループにおける知財活動の取り組みを紹介します。
【講演項目】
1.日揮グループの紹介と体制
1.1 日揮グループの紹介
1.2 知的財産部の組織体制
1.3 日揮グループにおける知財・無形資産の重要性
1.4 事業戦略・開発戦略と連動した知財戦略
1.5 知財インテリジェンス活動の目的・狙い
2.知財インテリジェンス活動を社内浸透させる施策
2.1 活動の周知
2.2 事業部門との連携
2.3 活動の多様化
2.4 活動の評価
2.5 インテリジェンス機能の強化
3.知財インテリジェンス活動の内容
3.1 知財戦略の遂行スキームとの関係
3.2 活動の進め方
3.3 コア事業領域における活動
3.4 成長・将来事業領域における活動
3.5 製造子会社とのシナジー
4.おわりに
【質疑応答】
---------------------------------------------------------------
【12月8日(月) 11:00~12:00】
【第4部】味の素グループにおけるIPランドスケープの活動と社内普及への取り組み
味の素(株) 知的財産部 企画戦略グループ シニアマネージャー 田澤 陽子氏
味の素(株) 知的財産部 企画戦略グループ マネージャー 大西 愛氏
【講師略歴】
田澤 陽子氏:大学卒業後、味の素(株)に入社。研究所勤務を経て知的財産部にて、知財戦略立案・推進、競合品対策、特許調査に従事。 味の素冷凍食品(株)へ出向し知財部門の立ち上げと統括を担当後、2023年7月より現職にて知財のビジネス活用、IPランドスケープを推進。
大西 愛氏:大学卒業後、2007年より味の素グループにて主にバイオ分野の特許調査・解析業務に従事。2017年弁理士登録。 2023年7月より、味の素(株) 知的財産部企画戦略グループのマネージャーとしてIPランドスケープの実行及び推進を担当。
【講演趣旨】
味の素グループは、知的財産を価値創造の源泉と位置づけ、従来の「守り」だけでなく、事業・R&D・知財が三位一体となった「攻め」の知財戦略を推進している。その中で、IPランドスケープ活動を「攻め」の知財戦略のトリガーとして位置づけ、事業戦略やR&D戦略の立案・意思決定に資することを目指して取り組んでいる。多くの先行企業の活動から学びつつ、当社らしいIPランドスケープ活動を確立すべくTry&Learnの姿勢で実践を重ね、徐々に成果が生まれている。本講演では、味の素グループにおけるIPランドスケープ活動の全体像と、具体的な活動事例、社内普及へ向けた取り組みについて紹介する。
【講演項目】
1.味の素グループの事業と成長戦略
2.知財戦略とIPランドスケープの位置づけ
3.IPランドスケープの具体的活動事例
3.1 成長領域での戦略方向性提案
3.2 GHG削減技術に関する事業機会探索
3.3 事業提携パートナー探索
3.4 競争優位確立に向けた技術開発・特許出願戦略
4.社内普及への取り組み
4.1 社内連携
4.2 IPランドスケープ実行体制
4.3 高度化・効率化の取り組み
4.4 人財育成・スキル向上
5.これまでの成果と今後の展望
【質疑応答】
---------------------------------------------------------------
【12月8日(月) 13:00~14:30】
【第5部】意思決定エンジンとしてのIPランドスケープ
~IMS基盤によるデータ駆動型R&Dマネジメント~
(株)フジクラ 基盤技術センター 知的財産渉外部 主席研究員 東村 恵理氏
【講師略歴】
東京大学大学院(化学生命工学専攻)、航空宇宙技術研究所(現JAXA)での経験を通じて生命科学の専門性とデータ分析能力を修得。これらの知見を基に国内大手特許事務所にてバイオ・化学材料業界の技術動向分析・特許戦略策定に従事。その後大手化学材料メーカーにてIPランドスケープの実行体制を整備、中小企業では知財インテリジェンス課立ち上げを主導するなど、企業内における知財情報活用基盤構築の実績を積む。現在、株式会社フジクラにて全社的なIPランドスケープ活動を推進。AIPE認定知的財産アナリスト。
【講演趣旨】
本講演では、フジクラにて2024年度より導入したISO 56002準拠のイノベーション・マネジメント・システム(IMS)を基盤としたIPランドスケープ(IPL)の実装について解説する。データ駆動経営を実現するため、IPLを「意思決定エンジン」として組織に組み込み、DELTAフレームワークによる実装設計、イベント起点の3層ゲート運用、最小人数でのキーパーソン設計を採用した。数値偏重を避けた質的KPI設計と、R&D最小実装から事業接続への段階的拡張アプローチにより、少人数体制でも迅速かつ再現性の高い意思決定を実現する方法論を共有する。
【講演項目】
1.イントロダクション:なぜIMS×IPLなのか
1.1 フジクラの技術開発における課題認識
1.2 データ駆動経営への転換の必要性
2.ISO 56002とIPLの統合フレームワーク
2.1 IMS「意思決定エンジン」としてのIPL
2.2 ISO 56002の8原則とIPLの関係性
2.3 PDCAサイクルへのIPL組み込み
3.DELTAによる実装設計
3.1 DELTAフレームワークとは
3.2 Data:再現性の基盤づくり
3.3 Enterprise:組織への組み込み戦略
3.4 Leadership:問いの定義と責任の明確化
3.5 Targets:STP分析による評価基準設定
3.6 Analysts:意味づけの設計者としての役割
4.IMSに組み込むIPLの4層アーキテクチャ
4.1 第1層:データ層(比較可能性の担保)
4.2 第2層:分析層(STPインサイトの生成)
4.3 第3層:マネジメント層(意思決定への接続)
4.4 第4層:ガバナンス層(原則と責任の明確化)
5.イベント駆動の3層ゲート運用
5.1 データ統制ゲート:再現性の保証
5.2 仮説検証ゲート:So What?の収束
5.3 資源配分ゲート:行動選択と投資判断
6.キーパーソン設計とRACI
6.1 旗振り役・橋渡し役・調査分析役の3役構成
6.2 少人数体制での連携モデル
7.数値に頼らないKPI設計
7.1 フェーズ1:質的KPIによる流れの固定
7.2 フェーズ2:量的KPIの段階的導入
8.ロードマップと今後の課題
8.1 R&D最小実装から事業接続への3段階
8.2 7つの壁:品質・文化・連携を越えるために
9.まとめ:小さく始めて確実に動かす
9.1 実装型データ駆動経営への道筋
【質疑応答】
---------------------------------------------------------------
【12月8日(月) 14:45~16:15】
【第6部】ブラザー工業におけるIPランドスケープの社内普及と定着
ブラザー工業(株) 知的財産部 グループ・マネジャー 伊藤 隆氏
【講師略歴】
技術者としてメーカー勤務を経て、2003年6月にブラザー工業株式会社へ入社。以降、知的財産部にて特許出願・調査、日英翻訳、ドイツでの特許権侵害訴訟等の業務に従事。2016年2月から2019年3月までは中国販社に出向し、模倣品対策や特許権侵害訴訟等の現地対応を担当。2019年4月以降は、特許・意匠・商標の出願・調査、模倣品対策、社内教育、IPランドスケープ活動等のマネジメントを行っている。
【講演趣旨】
本講演では、ブラザー工業におけるIPランドスケープの社内普及と定着の歩みを、現場の視点からご紹介します。弊社のIPランドスケープ活動は、知財部員によるボトムアップ型のチャレンジから始まり、独自のブランド「IPXNavi(IPクロスナビ)」として社内認知を獲得し、事業部・開発部の意思決定をナビゲートする存在へと成長しました。活動の成り立ち、普及施策、成果の測り方、今後の展望まで、具体的な事例や工夫を交えながら、IPランドスケープの実践と社内定着のポイントを紹介します。IPランドスケープ活動の社内浸透に悩む方々の一助となれば幸いです。
【講演項目】
1.ブラザーの紹介
2.IPランドスケープ活動のネーミングと社内ブランディング
3.IPランドスケープ活動のなりたち
4.IPランドスケープ活動のビジョン
5.IPランドスケープ活動の普及
6.IPランドスケープ活動の道しるべ
7.IPランドスケープ活動の拡大への対応
8.Pランドスケープ活動の成果の測り方
9.IPランドスケープ活動の現在地と今後の展望
【質疑応答】
セミナーの詳細についてお気軽にお問い合わせください。
2名以上同時にお申込される場合、2人目以降の方の情報は、
【弊社への連絡事項がございましたら、こちらにお書きください】欄に
ご入力をお願いいたします
◆Live配信セミナーについてのお願い◆
■お申込み前にご確認ください
・パソコンもしくはタブレット・スマートフォンとネットワーク環境をご準備下さい。
快適に視聴するには30Mbbs以上の回線が必要です。
・Zoomを使用されたことがない方は、ミーティング用Zoomクライアントをダウンロードして下さい。
ダウンロードできない方はWebブラウザ(Google Chrome、Firefox、Microsoft Edge)でも受講可能です。
Zoomの視聴にあたり、クライアントおよびWebブラウザは最新版にアップデートして使用してください。
・質問の際など、クリアな音声で会話ができるよう、ヘッドセット(イヤホンマイク)の使用をお勧めいたします。
・Zoomの使用方法につきましては、事前にWeb等でご確認ください。
下記公式サイトから視聴環境をご確認いただけます。
→視聴環境 https://zoom.us/test
■Live配信セミナーの受講について
・開講日の4~5日前に視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。
セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
・出席確認のため、視聴サイトへのログインの際にお名前、ご所属、メールアドレスをご入力ください。
ご入力いただいた情報は他の受講者には表示されません。
・開催前日着までに、製本したセミナー資料をお申込み時にお知らせいただいた住所へお送りいたします。
お申込みが直前の場合には、開催日までに資料の到着が間に合わないことがあります。
・当日は講師への質問をすることができます。
・本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。
・本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。
複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。
- サイト内検索
- セミナー・書籍新着情報
-
- 【Live配信セミナー 1/23】自動車リサイクルの課題、展望と 樹脂リサイクル技術の開発動向 (2025年11月28日)
- 【書籍】樹脂/フィラー複合材料の界面制御と評価(No.2157BOD2) (2025年11月18日)
- 【Live配信 or アーカイブ配信 1/29】GMP SOP(標準作業手順書)の必要性とその動画化の効果 (2025年11月14日)
- 【Live配信 or アーカイブ配信】パルスNMRによる高濃度分散体の分散状態および各種材料の「ぬれ性」評価,HSP値評価への応用 (2025年11月12日)
- 【Live配信セミナー 1/19】「レアメタル」,「レアアース」の概況,リサイクルの動き,輸出規制対応や市場展望/ (2025年11月12日)
- カテゴリー別
- 技術情報協会アーカイブ



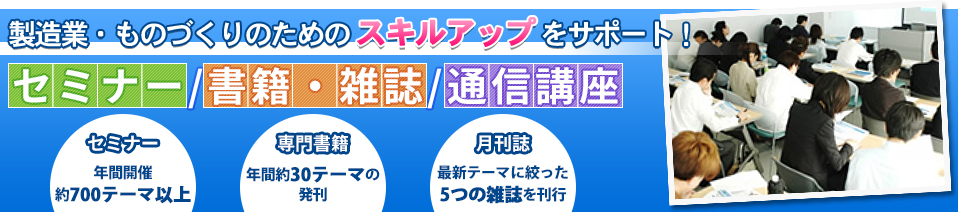

![足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内] 足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内]](https://www.atengineer.com/pr/gijutu/color/images/btn_wps.png)