| イベント名 | 水電解技術の開発動向と触媒材料の長寿命、高効率化への展望 |
|---|---|
| 開催期間 |
2026年01月19日(月)
9:50~16:20 |
| 会場名 | ZOOMを利用したLive配信 ※会場での講義は行いません |
| 会場の住所 | 東京都 |
| お申し込み期限日 | 2026年01月16日(金)15時 |
| お申し込み |
|
<セミナー No.601414>
【Live配信のみ】 アーカイブ配信はありません
水電解技術の開発動向と
触媒材料の長寿命、高効率化への展望
★グリーン水素製造に向けた水電解の現状と触媒材料への要求特性とは?
★水素クロスオーバーを防ぐ電極触媒、省イリジウム触媒についても解説
■ 講師
1.敬愛技術士事務所 所長 技術士(化学部門) 森田 敬愛 氏
2. 九州大学 高等研究院 大学院総合理工学研究院 准教授 博士(理学) 草田 康平 氏
3. 山梨大学 クリーンエネルギー研究センター 水素・燃料電池ナノ材料研究センター 教授 博士(工学) 柿沼 克良 氏
4. 田中貴金属工業(株) 製造統括部 FC触媒開発センター 主任 有馬 一慶 氏
5. 東ソー(株) 南陽事業所 無機材料研究所 環境エネルギーG 主任研究員 三島 崇禎 氏
■ 聴講料 :
1名につき66,000円(消費税込・資料付き)
〔1社2名以上同時申込の場合1名につき60,500円(税込)〕
〔大学、公的機関、医療機関の方には割引制度があります。
詳しくはお問い合わせください〕
※定員になり次第、お申込みは締切となります。
■ プログラム
<9:50~11:20>
1.水電解技術の基本と課題および今後の展望
敬愛技術士事務所 森田 敬愛 氏
【講演ポイント】
「カーボンニュートラル社会」を目指して世界中で様々な施策が進んでいます。その中で再生可能エネルギーから製造される「グリーン水素」は、エネルギー媒体としてはもちろん、様々な産業に必要不可欠な原材料としてますます重要となっていきます。
本セミナーでは「グリーン水素」を製造する水電解技術について、水電解の原理や主に低温形の各種水電解法についての基本事項を説明します。また、日・米・欧の技術開発動向の概要や、貴金属材料の視点を中心に水電解技術の課題や今後の展望などを解説していきます。
【プログラム】
1.水電解の基本
1.1 電解に必要なエネルギー
1.2 各種水電解法の概要
1.3 水素製造電力原単位
1.4 水電解効率
2.各種水電解法の基本
2.1 アルカリ水電解(AWE)
2.2 プロトン交換膜形水電解(PEMWE)
2.3 アニオン交換膜形水電解(AEMWE)
3.水電解の最近の研究開発動向
3.1 日本の動向(NEDOプロジェクト等)
3.2 米国の動向(DOEプロジェクト等)
3.3 欧州の動向(EUプロジェクト等)
4.水電解の課題
4.1 水電解水素の現状と将来
4.2 PEM形水電解の課題?貴金属の視点より
4.3 PFAS規制の動向
4.4 NEDO技術開発ロードマップ
4.5 水電解技術の今後の展望
【質疑応答】
-----------------------------
<11:30~12:30>
2.多元素ナノ物質を基軸とした水電解触媒の開発動向
九州大学 草田 康平 氏
【講演ポイント】
水電解技術は電力エネルギーにより水を分解して化学エネルギーである水素を製造するプロセスであり、CO2排出量ゼロ実現へ大きく貢献する技術として注目を得ている。 しかしながら、反応を促進する触媒の高コストと低性能が課題となっている。
演者らは、原子からボトムアップで粒子を構築する化学的合成手法を構築することを通して、バルクでは得られないようなナノ物質開発を行い、それらの触媒応用を研究している。
本講演では,多元素ナノ物質を基軸とした水電解触媒の開発動向について解説する。
【プログラム】
1.はじめに
2.化学的合成手法による新規ナノ粒子開発
3.多元素ナノ物質の水電解触媒応用
4.その他ナノ物質の水電解触媒応用
5.今後の展望
【質疑応答】
------------------------------
<13:30~14:30>
3.セラミックナノ粒子を用いた水電解用高活性・高耐久性触媒の創製と今後の展望
山梨大学 柿沼 克良 氏
【講演ポイント】
固体高分子形水電解(PEMWE)は高純度かつ高効率に水素を製造することができ、MWクラスからGWクラスでの実用化が求められている。その際の課題の一つがアノードの高機能化である。特にIrOx触媒の利用量削減と触媒活性の向上、そして、耐久性の向上が必要とされている。それらにアプローチする新しい触媒の紹介と量合成について説明する。
【プログラム】
1.ItOxナノ粒子担持セラミック触媒の合成と物性の説明
2.上記触媒の電気化学的活性評価
3.上記触媒のセル性能評価
4.近年の報告例との比較と高性能発現要因とメカニズムの説明
【質疑応答】
----------------------------
<14:40~15:10>
4.水素クロスオーバーを防ぐPEM形水電解用電極触媒の開発
田中貴金属工業(株) 有馬 一慶 氏
【講演ポイント】
近年、環境およびエネルギー問題解決のために再生可能エネルギーの余剰電力を利用し、水素製造と貯蔵を行い、必要な時にエネルギー源として利用するPower to Gas(P2G)が注目されている。P2Gでプロトン交換膜形水電解は、水から酸素ガスと水素ガスを生成する重要な役割を持つ。しかし、実用化には電解中に生成した水素ガスが隔壁(プロトン交換膜)を透過し酸素ガス発生側へ移動する“水素クロスオーバー現象”が爆発等の危険性があることから技術課題の1つになっている。
上記技術課題を解決するため、透過した水素を酸素と再結合させ、爆発を伴わずに水に戻す機能を水電解触媒に付与した”Bifunctional触媒“を開発した。当該触媒技術は、今後の水素社会実現に向けて大きく貢献できる見通しである。
本講演では当該開発触媒の詳細について述べる。
【プログラム】
1.田中貴金属工業の紹介
2.PEM形水電解とは
2.1 様々な水素製造方法
2.2 PEM形水電解の基礎技術
3.田中貴金属のPEM形水電解用電極触媒 紹介
3.1 既存触媒の紹介
3.2 実用化への課題(水素クロスオーバー)
4.Bifunctional触媒 紹介
4.1 開発コンセプト
4.2 Gas Recombination(GR)触媒
4.3 Bifunctional触媒
4.4 PEM形水電解システムでの特性評価
5.まとめ
【質疑応答】
-----------------------------
<15:20~16:20>
5.マンガン酸化物を用いたPEM型水電解用アノードの省イリジウム化技術の開発動向
東ソー(株) 三島 崇禎 氏
【講演ポイント】
カーボンニュートラル社会の実現には水素の大量導入が必要とされており、水素の製造方法としては、固体高分子型(PEM型)の水電解法が有望である。しかしPEM型水電解では希少なイリジウム(Ir)を触媒として使用するという課題があるため、Irの使用量を削減した触媒の開発が進められている。
国立研究開発法人理化学研究所では、二酸化マンガン(MnO2)を担体に用いた省イリジウム触媒(Ir-MnO2)を開発しており、我々は電解二酸化マンガンのメーカーとして、その工業化を検討している。本講演では当該開発触媒の詳細についてご紹介する。
【プログラム】
1.カーボンニュートラルと水素
2.水素とイリジウム
3.会社紹介
4.イリジウムフリー触媒
5.省イリジウム触媒
6.まとめ
【質疑応答】
セミナーの詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
- サイト内検索
- セミナー・書籍新着情報
-
- 【Live配信セミナー 2/17】 先端半導体デバイスにおけるCu/Low-k多層配線技術と2.5D/3Dデバイス集積化技術の基礎~最新開発動向 (2025年12月14日)
- 【Live配信セミナー 2/13】「光電融合」【光チップレット/Co-Packaged Optics】 に関するデバイス,材料,接合,回路技術の動き,その評価解析 (2025年12月14日)
- 【Live配信 or アーカイブ配信 2/13】 フィラー表面処理・分散技術の考え方,処方テクニック,分散評価 (2025年12月14日)
- 【Live配信 or アーカイブ配信 2/10】高分子における「ぬれのダイナミクス」の基礎とその評価・応用技術 (2025年12月14日)
- 【Live配信セミナー 2/5】~プラスチック,フィルム,ゴム,コーティングなど~ 高分子の(黄変・ピンク変など) 変色・劣化の発生メカニズム,変色箇所の評価,その対策 (2025年12月14日)
- カテゴリー別
- 技術情報協会アーカイブ



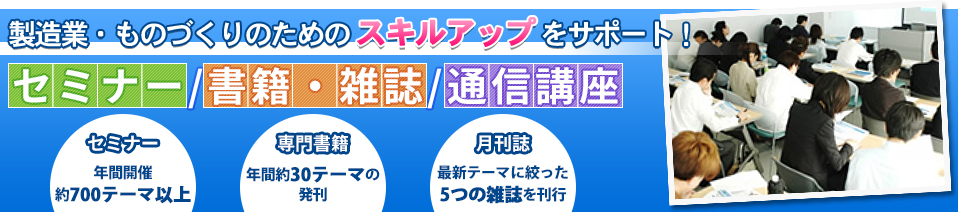

![足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内] 足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内]](https://www.atengineer.com/pr/gijutu/color/images/btn_wps.png)