| イベント名 | バイオミメティクス(生物模倣)の研究動向と機能材料設計への応用 |
|---|---|
| 開催期間 |
2025年10月03日(金)
10:30~16:30 |
| 会場名 | ZOOMを利用したLive配信 ※会場での講義は行いません |
| 会場の住所 | 東京都 |
| お申し込み期限日 | 2025年10月02日(木)15時 |
| お申し込み |
|
<セミナー No.510411>
【Live配信のみ】 アーカイブ配信はありません
バイオミメティクス(生物模倣) の
研究動向と機能材料設計への応用
★バイオミメティクスの最新動向と機能性材料応用に向けた解説
■ 講師
特定非営利活動法人バイオミメティクス推進協議会 事務局長 工学博士 平坂 雅男 氏
■ 聴講料 :
1名につき55,000円(消費税込・資料付き)
〔1社2名以上同時申込の場合1名につき49,500円(税込)〕
〔大学、公的機関、医療機関の方には割引制度があります。
詳しくはお問い合わせください〕
※定員になり次第、お申込みは締切となります。
■ プログラム
1. バイオミメティクスの発展
20世紀初頭に登場したバイオミメティクス(生物模倣)は、生物の形態や機能を模倣することで技術革新を目指す、学際的な分野として発展してきました。2000年代以降、ナノテクノロジーの進展によって生物観察技術が大きく進歩し、バイオミメティクスは新たな応用領域へと拡大しています。特に、生物多様性や環境保全が国際的な課題として注目される中、欧州では国家プロジェクトとしての支援体制が整備されました。現在では、材料開発や環境技術などを中心に、バイオミメティクスは多岐にわたる産業分野で期待されており、次世代イノベーションの源泉として位置づけられています。
2. 技術領域別の応用展開:材料、構造、表面機能、動き、センシング
バイオミメティクスの産業応用は、材料、構造、表面、モーション、センシングといった技術領域ごとに多様に展開されています。材料分野では、ハスの葉を模倣した超撥水性表面(ロータス効果)、モルフォチョウに由来する構造色、骨や貝殻に学んだ軽量高強度の複合材料などが実用化されています。構造分野では、サメ肌に着想を得たリブレット構造が航空機や水中ロボットの摩擦抵抗低減に貢献しています。表面機能では、光干渉を応用した色彩制御や自浄機能が注目されています。また、動物の関節構造や植物の屈曲運動に基づくアクチュエーターの開発、昆虫の感覚器を模倣したセンシング技術なども、ロボティクスや環境モニタリング分野で応用が進みつつあります。生物の機能の模倣がどのように技術革新につながるか、具体例を通じて紹介します。
3. 新たな展開:SDGsとバイオミメティクス、そして、情報科学へ
バイオミメティクスは、持続可能な社会の実現と高い親和性により国際的な注目を集めています。環境負荷を最小限に抑える材料開発、再生可能資源の模倣、エネルギー効率の高い構造設計といった研究への展開が進んでいます。これまでの構造の模倣にとどまる第1世代、動的機能を取り入れる第2世代を経て、現在では生態系や環境との相互作用全体を模倣する第3世代のバイオミメティクス(エコミメティクス)へと進化しようとしています。加えて、AIやデジタル技術と融合することで、生物の行動や形態をデータとして解析し、設計支援や自律的機能の創出へつなげる研究も加速しています。これらの新しい潮流について具体的な事例とともに解説します。
4. 産業応用と課題:分野別動向と海外動向
産業界においては、繊維、建築、モビリティ、エレクトロニクス、医療などの分野でバイオミメティクスの活用が進められています。これらの産業応用事例を紹介するとともに、欧州を中心とした海外の最新動向についてもレビューします。また、第2世代の代表的応用である「動的機能表面」については、その市場ポテンシャルや適用事例についても紹介します。一方、バイオミメティクスは異分野融合領域であるため、生物学と工学の間に「翻訳者」が不足しているという課題があります。この課題の解決に向けて、情報科学の活用や人材育成の取り組みが求められています。実際に、イノベーション実現には多様な専門性を持つ人材とステークホルダーの連携が鍵となっており、分野横断的なネットワーク構築の重要性が高まっています。
5. 国際標準化と今後の展望:ISO/TC266の動向
バイオミメティクスの産業応用を推進するうえで、国際標準化は極めて重要な役割を担っています。ISO/TC266(バイオミメティクス技術委員会)は2011年に設立され、方法論、用語、設計指針、製品適用プロセスなどに関する国際規格の整備が進められてきました。日本からも積極的な提案がなされており、現在は「動的機能表面」の設計に関する国際標準化活動が進行中です。一方、ドイツや中国からの新たな提案もあり、それに対する日本の戦略的対応が今後の課題となっています。国際標準化は単なる技術規格にとどまらず、イノベーションを支える基盤として、多国間連携や標準間の整合性も含めた戦略的な活動が求められています。本講では、ISO/TC266の具体的活動内容と、関連する他の国際標準化の動きについても紹介します。
最後に最新のトピックスについても紹介する予定です。
【質疑応答】
セミナーの詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
- サイト内検索
- セミナー・書籍新着情報
-
- 【Live配信セミナー 11/17】 核剤(結晶核剤),造核剤の種類と使い方,高分子の結晶化制御,各種応用,その評価法 (2025年09月08日)
- 【Live配信 or アーカイブ配信】「UV硬化」の硬化不良,トラブルの種類とその対策,硬化物性の測定評価 (2025年09月08日)
- 【Live配信 or アーカイブ配信】新しいリチウムイオン電池の電極構成,特性と材料&プロセス技術 ~双極子and全固体with乾式電極withoutバインダー~ (2025年09月08日)
- 【Live配信 or アーカイブ配信】乳化(エマルション),可溶化,ゲル化のメカニズム,乳化剤の種類と選定,安定化,その評価 (2025年09月08日)
- 【セミナー 11/6】微粒子の分散・凝縮メカニズム,安定化,評価 (2025年09月08日)
- カテゴリー別
- 技術情報協会アーカイブ



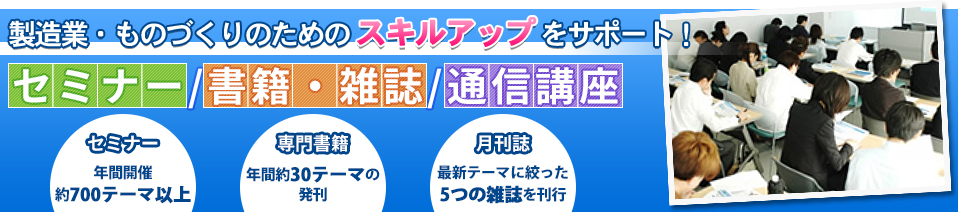

![足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内] 足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内]](https://www.atengineer.com/pr/gijutu/color/images/btn_wps.png)